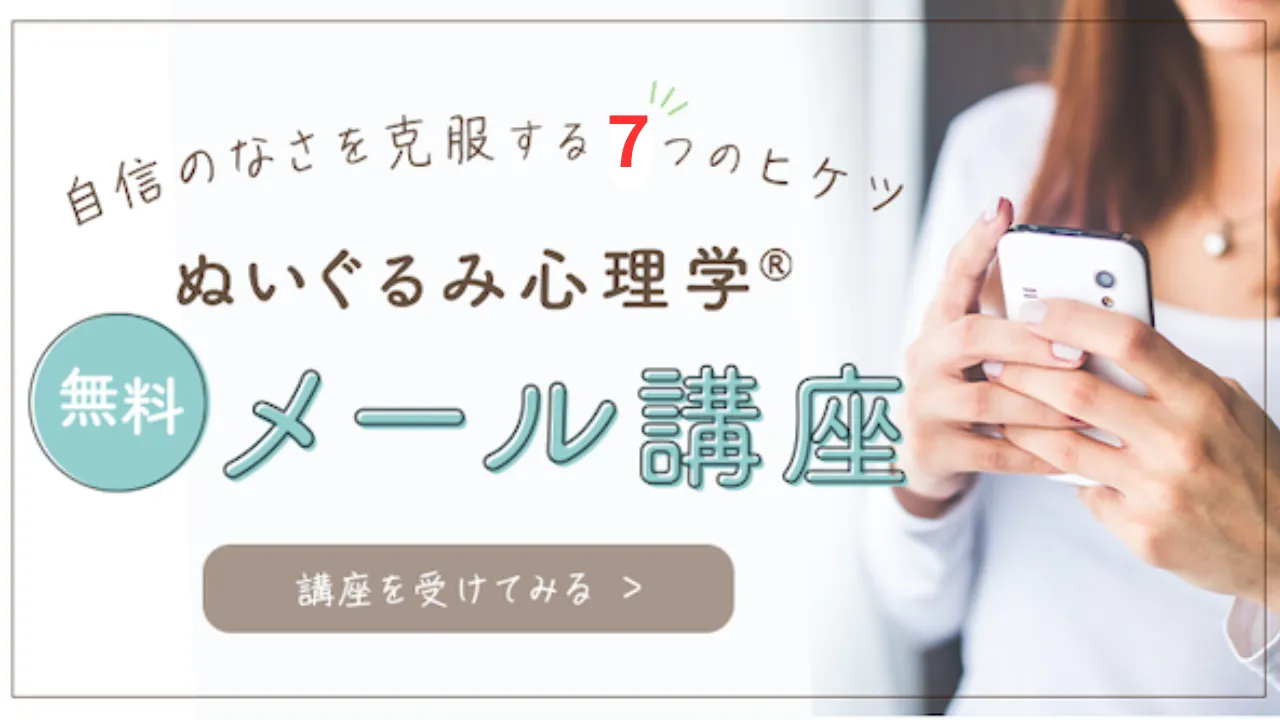7Apr
[最終更新日]2025/09/22

こんにちは、伊庭和高です。
「自分に自信が持てない」という声は、
私の元にもよく寄せられています。
仕事でもプライベートでも、
自信がないと物事は上手く進みません。
そして自信のなさは人間関係にも影響を与えます。
「人と話すとドキドキしてしまう」
「相手にどう思われるか怖くて会話を避けてしまう」
「人と関わるのが怖い」という声も、
自信が持てず悩んでいる人からよく聞きます。
なぜ自信のなさが「人が怖い」につながるのか、
今回の記事ではぬいぐるみ心理学の視点から、
心理学的な理由と具体的な対処法を紹介します。
安心して人間関係を築けるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
「自信がない」と人が怖くなる5つの理由
自分に自信がないと人が怖いと感じるのは、
大きく5つの理由があります。
どれか1つに当てはまることもあれば、
複数に該当することもあります。
1、怒られるのが怖い
自分に自信が持てないと、
怒られるのを怖がってしまいます。
「怒られた=悪いことをした」と思い込み、
つい萎縮してしまうのです。
怒られるのを怖がっていれば、
同時に人と関わること自体も怖がります。
怒られない様に予防線を張ったり、
できる限り距離を取ろうとするのです。
2、自分軸がない
「言いたいことがわからない」
「やりたいことがわからない」
「意見がない」
この様に自分軸がないままだと、
人と関わるのを怖がります。
相手に何かを言われても、
自分軸がないと反論できないのです。
一方的に責められている様に感じたりと、
人と関わる中で息苦しさを感じやすくなります。
3、他人の評価を気にしすぎる
「変な風に思われたらどうしよう…」
この様に他人の評価を気にしすぎると、
人と関わるのが怖くなってしまいます。
自信がないと「どう思われるのか?」が気になるのです。
どれだけ相手のことを考えても、
相手の気持ちは相手にしかわかりません。
永遠に答えがわからない問題を解いている様なものなのです。
そして他人の評価を気にするほど、
「嫌われているに違いない」と悪く解釈しやすくなります。
これは心理学でいう認知のゆがみであり、
現実よりも否定的に受け取る傾向が強まります。
これではますます人が怖くなってしまいます。
4、本当の自分を知られるのが怖い
自分の気持ちを抑えていたり、
偽りの自分を演じている人ほど、
人と関わるのが怖くなります。
たとえ表面的な関係は築けても、
深い関係になるのを怖がっているのです。
関係が深くなればなるほど、
本当の自分を知られる可能性があります。
自分に自信がないからこそ、
本当の自分を知られることが怖いのです。
5、過去の失敗体験が影響している
「人前で失敗した」
「誰かに強く否定された」
こうした経験は強く心に残ります。
その記憶がトラウマのように働き、
「また失敗するのでは」と不安を引き起こします。
心理学ではこれを学習性無力感と呼び、
似た状況に直面したとき自動的に不安が湧きやすくなります。
人が怖いと感じやすい具体的な場面
ここまで5つの心理的な理由を紹介しましたが、
人が怖いと感じやすい具体的な場面を紹介します。
仕事での人間関係
たとえば仕事で人が怖くなるのは、
次のような瞬間です。
「上司や同僚に報告するとき、緊張して言葉が出なくなる」
「ミスを恐れて質問できず、さらに不安が強まる」
「役職についたけど、周囲の評価が気になり指示が出せない」
「過去の失敗経験から、営業先へ訪問するのが怖い」
このように仕事の場面では評価が伴うため、
人が怖い感情が出やすいのです。
人間関係
「嫌われるのを怖がり話しかけられない」
「周りにどう思われるか気になり孤立してしまう」
「過去に喧嘩した経験を引きずり自信が持てない」
こうした気持ちを抱くほど、人が怖くなります。
生きている限り、人間関係は続きます。
付き合う相手や環境を変えても、
人間関係がなくなることはありません。
直接関わる人だけでなく、
SNSやメディアで間接的に関わる人間関係も影響を及ぼすのです。
恋愛
仕事や人間関係では問題ないのに、
恋愛になると自信がなくなる人は多いです。
「嫌われるのを怖がり相手に合わせてしまう」
「どうせ好かれないと思い自分からアプローチをしない」
自信のなさから恋愛にも恐怖心が生まれ、
うまくいかない恋愛を繰り返すことがあります。
自信のなさが悩みの根本原因
私はぬいぐるみ心理学において、
すべての悩みの原因は自信のなさだとお伝えしています。
詳細は無料メール講座でも解説していますが、
人が怖いのも自信のなさが影響しています。
自信がないままでも生きていけますが、
同じ悩みを繰り返してしまいます。
仕事、恋愛、人間関係など、
場面を変えて人が怖くなってしまうのです。
人が怖いと感じる状況は、
時間が解決してはくれないのです。
また私は、自分の自信のなさの度合いを診断する心理テストを開発しました。
12個の質問(二択)に答えるだけで、
自信のなさをどれだけ感じているかが判明します。
こちらも合わせてやってみてください。
幼少期の記憶が影響している
私たちの自信のなさは、
幼少期の経験で形作られます。
生まれた時から自信がない人はいません。
泣きたい時は泣き、
笑いたい時は笑い、
欲しい物は欲しいと主張していました。
ですが成長する中で少しずつ、
自信がなくなり人が怖くなるのです。
また私たちにとって親との関係が、
すべての人間関係のスタートです。
親の顔色を伺っていたり、
怒られない様に意識していたり、
親も人と関わるのを怖がっていると、
子供も人と関わるのが怖くなってしまうのです。
ただし冷静に考えれば、
生まれた時から人が怖いと思うことはありません。
人が怖いのは生まれ持った性格ではなく、
後天的に身についてしまっただけなので、
誰でも今から克服できるのです。
人が怖いときにできる即効対処法
「どうすれば自信を取り戻せるのか?」
「人が怖くならない方法は何か?」
こうした相談は多いです。
自信を取り戻すための方法は、
世の中に数多くあふれています。
・呼吸を整えて体をリラックスさせる
・相手は相手だと割り切る
・小さな成功体験を積む
・自分に良い言葉をかけてあげる
・ポジティブ思考をする
・自信のある自分をイメージする
これらは一例ですが、実践すれば一時的に効果は出るでしょう。
ですが一時的に自信を取り戻せても、
自信が持続せず頭を抱えている人は多いです。
これらの方法は栄養ドリンクの様なものです。
一時的に元気になれるものの、
いずれ効き目は切れてしまいます。
根本的な自信にはつながらない
栄養ドリンクを飲まなければいけない原因にアプローチすること。
これこそが人を怖がるのを克服し、
自信を取り戻すために必要なことです。
先ほど紹介した方法は自信が持続しないという問題点を抱えています。
私はぬいぐるみ心理学において、
取り戻した自信が持続する方法を開発しました。
だからこそ人が怖い悩みも根本解決できるのです。
一時的に自信を持つのではなく、
どんな時でも自信のある状態でいるにはどうすればいいのか?
もし今後自信をなくすことがあっても、
すぐにリカバリーできる方法は何か?
これから2つ紹介します。
人が怖いのを克服する2つの方法
次にぬいぐるみ心理学の視点から、
人が怖いのを克服する方法をお伝えします。
2つの方法を繰り返し実践することで、
今から現状は変えられます。
ステップ1:自分で自分の気持ちを声に出す
まず最初に取り組むのは、
自分で自分の気持ちを声に出すこと。
人が怖いと思う時ほど、
自分の気持ちを声に出していません。
普段から声に出さず、頭の中で考えがちなのです。
私たち人間の脳は頭の中で考えるほど、
ネガティブ思考が強まる習性があります。
一説では1日に考えることの9割が、
ネガティブな事柄だと言われています。
ネガティブに考えるほど、
ますます人が怖くなり自信もなくなってしまうのです。
先ほど紹介した5つの理由も、
頭の中で考えている時に起こりがちです。
どんな気持ちでも大丈夫です。
まずは自分で自分の気持ちを声に出すことが、
現状を変える第一歩です。
頭に浮かんだ言葉を実況中継するイメージで、
ブツブツと独り言をつぶやいてください。
ちなみに自分の気持ちを声に出す上では、
ぬいぐるみを活用するのが効果的です。
詳細は無料メール講座でも解説していますが、
意識してぬいぐるみに触れることは、
自分の気持ちを声に出す上でも効果的です。
ステップ2:「どうしたい?」と問いかける
そして自分の気持ちを声に出した後は、
「どうしたい?」と問いかけます。
「どうしたい?」の主語は自分自身。
人が怖いと思う時ほど、
自分を主語に問いかけていません。
自分以外の誰かのことを考えています。
「した方がいい」
「するべきだ」
「しなければならない」
「してあげる」
「して欲しい」
たとえばこれらの言葉は、
自分以外の誰かのことを考えている時に浮かびます。
自分軸と他人軸という言葉がありますが、
まさに他人軸になっているので、
周りの目を気にしたり失敗を怖がりやすくなります。
また「どうしたいのか?」ではなく、
「どうすればいいのか?」と考えがちな人も、
自信がなくなる傾向があります。
「私はどうすればいいの?」という様に、
答えを周りに求め続けてしまうので、
周りの反応が怖くなりやすいのです。
「どうしたい?」と自分を主語に問いかけるのは、
人が怖いのを克服し自信を取り戻すために不可欠です。
人が怖いのを克服したお客様のエピソード
次にぬいぐるみ心理学のお客様で、
人が怖いのを克服できたエピソードを紹介します。
東京都在住の塩見さん(女性・仮名)は、
人と関わる時に緊張してしまったり、
つい相手の顔色を伺うことがありました。
「何とかして原因と改善策を知りたい」と思う中で、
私のことを知ってくださりました。
===ここから===
人が怖いと思う5つの理由を聞く中で、
「すべて当てはまってるじゃん」と思いました。
子供の頃から周りの目を気にしたり、
良い子でいなきゃと思っていました。
周りからどう見られるかや、
評価が下がらないようにと考え続けていました。
まさに他人軸になっていましたが、
社会人になり仕事をする中で誤魔化しがきかなくなりました。
意見が言えず合わせてばかりで、
「何を考えているかわからない」と上司に言われてしまいました。
また気を使い続けてばかりで、
仕事終わりに疲れがドッと出る状態でした。
勇気を出して意見を言おうと思っても、
「否定されたらどうしよう」と思い、
不安や恐怖心で言葉が出ない状態でした。
伊庭さんから自信のなさが原因だと教えてもらい、
私の中でも納得できました。
同時に自信がない状態は今から変えられると知り、
それなら今すぐにでも変わりたいと思いました。
===ここまで===
塩見さんに起こった変化
私は塩見さんのお話を聞く中で、
先ほど紹介した2つの方法をお伝えしました。
また塩見さんの状況に合わせて、
個別に取り組んで欲しい行動もお伝えしました。
ぬいぐるみ心理学を実践し始めて数週間で、
塩見さんは確かな手ごたえをつかまれました。
===ここから===
今までは声に出さず頭の中で考え、
不安や恐怖心を募らせてばかりでした。
独り言をぶつぶつと発したり、
ぬいぐるみとの関わりを持ち始めると、
今までより早く冷静さを取り戻せる様になりました。
声に出しながら気持ちを受け止め、
現状を整理して受け止められる様になったのです。
これに関しては知識で理解するだけでなく、
実際にブツブツ声に出さないと気づけなかったと思います。
そして自分を主語に問いかけることは、
今まで意識していませんでした。
まず周りにどう思われるかを気にして、
語尾が「〜したい」になっていませんでした。
自分軸を持ってコミュニケーションをとると、
今まで以上に会話がスムーズに進みました。
言いたいことにもすぐ気づける様になり、
否定されるのを怖がることもなくなりました。
「最近変わったね」と上司にも言われますし、
自分でも変化を実感できています。
自信がないから人と接するのが怖い状況は、
確実に、一気に変わっていると思います。
===ここまで===
まとめ
仕事でもプライベートでも、
人が怖いままでは苦しいです。
人間関係に悩んだり、
自己嫌悪の気持ちに襲われたりと、
生きづらさを感じる様になります。
悩みやストレスを定期的に感じてしまい、
幸せな未来は待っていないのです。
ただし自信のなさと向き合い、
先ほど紹介した2つの方法を実践すれば、
人が怖いと思う現状は改善できます。
根本原因である自信のなさと向き合い、
2つの方法を実践することで、
現状を好転していきましょう。
「自信のなさとは何なのか?」
「どうすれば自信が持てる様になるのか?」
詳細は無料メール講座でも解説しているので、
合わせて学んでみてください。
本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
このコラムの執筆者

伊庭 和高(いば かずたか)
自信の専門家。三重県鈴鹿市出身。その後、千葉県千葉市で育つ。
2人兄弟の長男として生まれ、幼い頃から50体以上のぬいぐるみがある部屋で育つ。
早稲田大学教育学部卒業、同大学院教育学研究科修了。
在学中は教育学、コミュニケーション、心理学に専念する。
人間関係の悩みを根本から解決する有効な手法として、ぬいぐるみ心理学という独自の理論を開発。
これまで9年間で7000名以上のお客様にぬいぐるみ心理学を提供。性別・年齢・職業を問わず多くが効果を実感しており、日本全国はもちろん、世界からも相談が後を絶たない。
2014年10月から始めたブログは、今では1000以上の記事があり、月に13万以上のアクセスがある。
2017年11月には株式会社マイルートプラスを設立。
心理コミュニケーションアドバイザーとして、受講者とぬいぐるみ心理学を通して実践的な関わりを続け、それぞれの「望む未来」の実現の手助けをしている。
2020年、初の著書『ストレスフリー人間関係〜ぬいぐるみ心理学を活用してあなたの人間関係の悩みを活用する方法〜』を出版。増刷しロングセラー中である。
2023年10月に三笠書房・王様文庫より『声に出すだけでモヤモヤがすっきりする本〜たった5秒のメンタルケア〜』を発売。
2025年9月にPHP研究所より『大人だって、ぬいぐるみに癒されたい!』を発売。
『女性自身』(2023年9月19日号)にて、カラー8ページでぬいぐるみ心理学が特集されるなど、活動の幅が広がっている。